ご覧いただきありがとうございます。
今回はプログラミングを自分なりに調べてみました。
理由は今後の成長を考えて、
学んだばかりのことを記事にしてみたいと思ったからです。
私の中で、今までのプログラミングのイメージといえば、
「あ、、なんかよく分からん文字でてきた、、、」
「うげ、なんじゃこりゃ、難しい!」
「もう、むりいいい!」
となってしまうので調べること自体を避けてました。
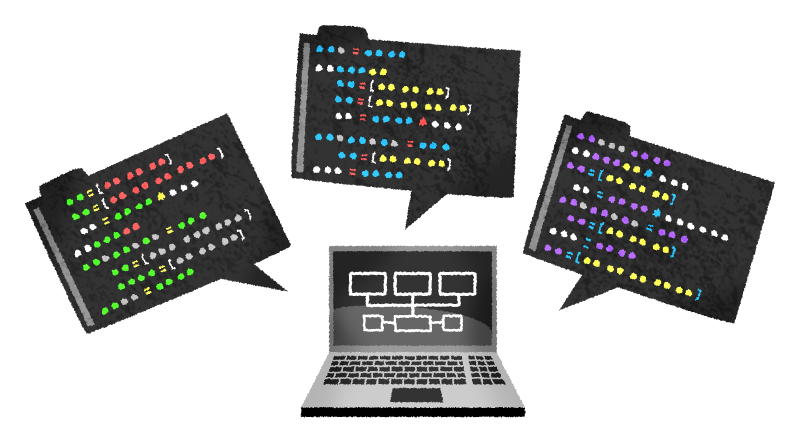
そんな私が執筆する記事なのでおそらく
プログラミングをよく知らないという方には
わかりやすい記事になるのではないでしょうか。
この記事が誰かの役に立てれば嬉しいです!それでは行ってみましょう!
Contents
人間の感覚、機械の感覚
まず「人間の感覚」と「機械の感覚」は違います。
今回はイメージしやすい料理でたとえてみます。
料理は慣れてない人でもレシピ通りに作ればそれなりのものが作れます。
でも作りたい料理を”擬人化したロボット”に作ってもらおうとすると
「え?何すればいいか分からん、、、」
となるはずです。
その”擬人化したロボット”に”こう動いてね”と指示をするのがプログラミングです。
ただ、指示をする、指示を受ける、と言っても人間と機械では情報の処理の仕方が全く違います。
人間は曖昧なものを曖昧なまま理解できます。
機械は具体的なものしか理解できません。
たとえば、「人参の皮をむいてください」と指示したときに
私たち人間は、どう動くかなんとなくビジョンが浮かぶはずです。
「まず皮むき器を手にとって、それから、、、」
はい!残念ながら機械はそれだけでは動けません。
ロボットに皮むき器を手にとってもらうには
「1メートル先のU字型の物体を自在に取り扱える範囲内で握ってください」
という指示をいくつもの変数のコードを入力して処理してもらう必要があります。
そのコードが少しでも間違っていたらバグが起きます。
たとえば、誤って皮むき器を吹き飛ばしたり、握ろうとして握りつぶしてしまったり、等です。
ざっくりいえば
ロボット等の機械に”理解してもらう””指示をする”
その架け橋となるのがプログラミングです。
まとめ
- 人間は抽象的なものを抽象的なまま
理解できる。 - 機械は具体的に言わないと理解できない。
- 機械に指示をする言葉がプログラミング
今後私たちの生活は機械によってますます便利なものになっていくと思われます。
しかし便利なものをただ扱うだけでなく
その裏にある技術もしっかりと理解しておくことが大事なのではないでしょうか。
私もまだまだ知らないことがたくさんあるので執筆活動を通して学びを得たいと思っています。
それでは今回はこの辺で終わりたいと思います!
最後まで読んでいただきありがとうございました。ではでは!